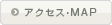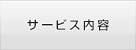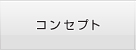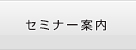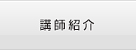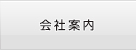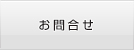「上司は、自分たち部下がどのように業務を進めているか、現場への理解が足りなくて困るよ」という管理職への不満を持つ部下も多いかもしれません。だからこそ、現場を理解してくれる管理職は部下にとって喜ばしいものです。一方で、多くの管理職は現場を理解しようと努力し、中には現場理解に自信を持つ管理職もいるでしょう。しかし、その現場理解は部下の成長や業務効果にうまく使われているのでしょうか。現場、部下を大切に考え、理解を深めている管理職だからこそ、やってしまいがちな落とし穴があります。ここでは、どのような落とし穴があるのか、それにどう対応すればいいのかについて考えていきます。
現場理解に自信がある管理職がやってしまいがちな落とし穴
部下の業務内容、現場への理解に自信がある管理職は、常に部下のことを考えている「良い上司」といえます。しかし、そんな管理職だからこそ、やってしまいがちな落とし穴が2つあります。ひとつは、現場を理解しているからこその落とし穴であり、もう一つは部下を大切にしているからこその落とし穴です。2つの落とし穴について考えていきましょう。
落とし穴1.詳細な指示をしてしまう
現場を理解しているから、依頼する業務に対し部下が何をすればいいのかが詳細にわかってしまう。だから詳細な指示を出してしまうことがあるというのが一つ目の落とし穴です。新入社員や若手社員にとっては詳細な指示はありがたいことでしょう。でも中堅社員にとっては自分たちのことを信用していないのかと疑われてしまいます。もちろん、新入社員や若手社員と中堅社員への指示の出し方については、各自の状況を理解して行っている管理職も多いかもしれません。しかし、現場を理解しているために無意識に指示が詳細になってしまう可能性はないとはいえないでしょう。
落とし穴2.打ち合わせは自分だけ参加する
現場を理解しているので、打ち合わせ後に部下に適切な指示が出せるという自信と、忙しい部下の時間を割きたくないという理由で、打ち合わせは基本、管理職の自分だけが参加するというのも、実は落とし穴になることがあります。現場を理解しているという自信はすばらしいものです。しかし、考えてみてください。たとえプレイングマネージャーのように自分が現場に立っていても、部下一人一人の詳細な業務を理解しきれているといえるのでしょうか。普段からその業務をしているからこそ気がつくこと、それを進めるために求める情報というものがあります。それをすべて把握することは管理職であっても難しく、打ち合わせ後に管理職が部下に出した指示の中に、実は業務を進めるために必要な情報、確認したい事項が含まれていないということも起こり得るのです。しかも、上司からの指示が明確であれば、部下は効果を最大限にするには、他にも必要な情報があるかもしれないという発想を持たない可能性もあります。その場合、得られるはずの効果に十分至っていない結果になったとしても、誰も気がつかないかもしれません。
落とし穴を避けるためには
現場を理解しよう、部下の状況を把握し負担をかけないようにしようという管理職の姿勢はすばらしいものです。落とし穴にはまらず、この努力を活かしていくために、どのようにすればいいのでしょうか。ここでは、対応策を考えていきます。
指示はポイントを伝え、質疑応答へ
先述のように詳細な指示が悪いわけではありません。特に詳細な指示を求める新入社員には、業務を覚えるためには必要なことでしょう。しかし、その新入社員であってもずっと詳細な指示を出し続けていては成長につながりません。そのため、部下のスキルや経験に合わせて指示の出し方を変えるといいでしょう。
この指示の出し方こそ、現場理解がある管理職の腕の見せ所となります。部下の成長に合わせて、どこまで詳細な指示をすると理解できるのかは現場を理解している管理職なら判断は容易かもしれません。それに加えて部下を成長させるために、指示の出し方に一工夫できるのも現場を理解している管理職だからこそできることです。指示はポイントだけ伝え(業務経験の多い中堅社員なら、どうしたいかという求める結果だけでもいいかもしれません)、業務を進めるうえで必要な情報を部下からの質問に答える形にするのです。それにより、十分な質問ができない部下には伝えるポイントを増やし、どんどん質問してくる部下には次回はもう少しあっさりした指示にするなど、成長度合いの確認の場にも使えます。
すべての指示に対して、このようなやり取りを部下とするのは難しいかもしれませんが、部下の成長度合いの確認をしたいという業務の時には、指示の出し方を工夫してみるのはいかがでしょうか。そして、指示の出し方を工夫する必要のない普段の部下への指示については、部下のスキルや経験を再度考え、詳細すぎる指示になっていないかを見直す癖をつけるのがいいでしょう。
業務を担当する部下を打ち合わせに参加させる
業務を担当する部下を打ち合わせに参加させましょう。もちろん、すべての打ち合わせに部下を参加させるべきだといっているのではありません。打ち合わせの中には、どんな施策にするか、案としてあがった施策を進めるか否かというような、どのような業務が発生して、誰が担当するのがいいかなどが明確になっていないものもあるでしょう。そのような打ち合わせに部下を参加させたら、現場に理解のある管理職が心配するように、忙しい部下の大切な時間を割くことになります。
施策を進める段階になったら、関係者との打ち合わせに業務を依頼する予定の部下を参加させることを検討するのがいいでしょう。部下の中には、打ち合わせで現場の立場から案を出し、どのような情報が必要なのかを物怖じしないで発言する人もいれば、話を聞いているのが精一杯の人もいるかもしれません。しかし、たとえ発言できなくてもどういう議論の中で、この施策を進めようとしているのかを肌で感じることが出来ます。打ち合わせに参加せずに上司から指示を受ける場合は、背景が十分理解できないまま業務を進めてしまう可能性もあり、その業務を担当しているからこそ思いつく提案にもつながらないことも考えられます。
打ち合わせに参加することで、例えば、自分の立場で何をしなくてはいけないのかを部下なりに考える機会になる、また、関係者と顔を合わせることで上司経由にしなくても部下が直接問い合わせや相談ができるようになります。これは業務効果を高め、部下の成長にもつながるといえるのです。「忙しい部下の代わりに自分が打ち合わせに出て話を聞いておこう」は業務の効果や部下の成長に影響を及ぼす可能性があることを鑑み、部下を打ち合わせに参加させるかどうかを検討することをお勧めします。
部下の能力を最大限発揮させ、業務効果を最大化しよう
現場を理解している管理職は部下にとっては喜ばしい上司といえます。現場を理解しているから、部下のことを考えているからこその落とし穴を避け、現場理解や部下への思いを部下の能力を発揮させることにつなげていきましょう。部下が能力を最大限に発揮できれば、業務効果も高まり、部下の成長にもつながるでしょう。
グローネス・コンサルティングでは25年以上の研修の実績があります。管理職向け研修、リーダー研修、新人研修など多くの研修プログラムを提供しています。各社に合わせたカスタマイズ研修の経験も豊富ですので、悩める管理職を元気にしたい!というご要望にも合わせたプログラムをご用意できます。部下育成や管理職としての役割などにお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。