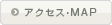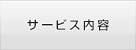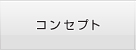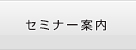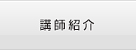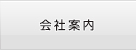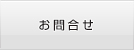新入社員から中堅社員と、会社の社員全体のなかでZ世代の割合が増えてきていることでしょう。ネットですぐに回答が得られる、動画で詳しくやり方を教えてくれることに慣れているZ世代は、業務も丁寧に教えてもらえることを求めます。しかし、その割合が増えてくると、すべてのZ社員にそのような対応をすることは難しくなります。また、Z世代の社員以外でも丁寧な対応を求めている部下は一定数いるものです。それでは管理職の負担は増えるばかりでしょう。
ここでは、Z世代をはじめ、丁寧な指導を求める人たちが「自立自走」し、管理職の負担を減らしていくために必要な3つのステップについて紹介します。
部下に求める「自立自走」とは
まず、部下に「自立自走」を求める理由を説明します。ビジネスにおける「自立」とは仕事の進め方や業務を一通り理解することで、ひとつひとつ指示をしなくても仕事ができる状態になることです。新入社員には、この「自立」が最初に求められることでしょう。しかし、「一人でできるようになること」=「ビジネスにおける成長」というには足りず、状況を把握し、自分で考えて行動できるようになって、初めて仕事を安心して任せられる人材といえるのではないでしょうか。この自分で考えて行動することが「自立自走」であり、部下が「自立自走」を身につけるために管理職が支援することが求められるといえるのです。
「自立自走」型人材育成の前提
3つのステップの前に、どのステップにも必要な管理職が行うべきことがあります。それは、どの世代の部下に対しても、何のためにその業務を行うのかという最終目的を伝えることです。自分で考え、行動する「自立自走」を求めることは、部下が自分で状況を把握し、ある基準で判断し、行動に移すことになります。もし、目的をしっかり理解していなければ、時として間違った判断基準のもと、会社の意向とは異なる行動をとってしまう可能性も否めません。そうならないためには、なぜそれをするのかを常日頃から伝える癖を管理職が持つ必要があるのです。
もちろん、Z世代をはじめとした社歴の短い部下にとっては、全体像や、なぜそれをするのかを伝えても、知識や経験不足で理解が十分にできるとは限りません。しかし、何度も伝えていくうちに、だんだんと理解が深まり、「自立自走」するころには会社の目的や意向をもとに考え、判断・行動ができるようになるでしょう。このような目的を理解して業務を遂行することは、部下が「自立自走」できるようになることにもつながります。管理職は「自立自走」できるようになってからでいいと後回しにせず、最初から部下に目的を伝えていくことが大切であるといえるでしょう。
部下の「自立自走」を支援する3つのステップ
自分で考え、行動する「自立自走」は簡単に身につくものではありません。そのため、管理職としては、順を追って「自立自走」する人材に部下を育成していきましょう。ここでは「自立自走」を支援する3ステップを紹介します。
ステップ1.まずはお膳立て
なんでも簡単に答えがネットで得られる環境で育ったZ世代の部下をはじめ、経験、知識が十分身についていない部下には、面倒と思っても一つ一つの業務を丁寧に教えましょう。手本を見せるのも大切です。もちろん、管理職がすべてを行う必要はなく、先輩社員に、後輩の指導時には丁寧に教える、手本を見せることを伝え、実践してもらうのもいいでしょう。また、自分から発言することに躊躇しがちなZ世代の部下には管理職、先輩から声をかけることで、業務の進捗などを把握し、適切なアドバイスをするように心掛けることも忘れないようにしましょう。
まずは、新入社員、社歴の短い社員が業務に慣れる、この会社でやっていけそうと思える環境にすることが大切になります。お膳立てにより部下の不安を取り除き、部下が業務に前向きに取り組めるようにしていきましょう。
ステップ2.質問の仕方を指導する
質問をすること自体に躊躇しているころは管理職、先輩から声をかけていきますが、徐々に声がけを減らし、部下から質問することを促すようにしましょう。最初は自分から質問できるようになることが大切です。的を射ていなくても、以前説明したことであっても、質問するようになったことを評価しましょう。わからないことがあったら、躊躇せず質問できるようにする、それが大切です。
しかし、いつまでも的を射ない、以前に説明したことについて質問しているだけでは、「自立自走」にはたどり着けません。ある程度、質問ができるようになったら、質問の仕方を指導していきましょう。当たり前のことですが、質問する前に自分なりに考えるという癖を部下につけさせるようにします。
最初は、質問されたときに、「あなたはどう思うのですか」と聞き返すのがいいでしょう。質問することにやっと慣れてきたころは、「あなたはどう思うか」と聞かれて、返答できる部下は少ないかもしれません。しかし、管理職が質問されるたびに、どう思うのかを聞くことで、部下は質問する前に自分なりの意見を持つことが必要であることを、少しずつでも理解していくことができます。自分で判断ができるようになるには、まず、自分で考えることができるようになることが大切です。
もちろん、急を要することについては、部下が考える時間を待っていることはできません。自分で考える前に報告を先にしなければならない案件があることも教えていくことが重要です。報告が先か、自分の考えをまとめてから質問すべきか、その判断が難しい場合は、迷わず報告するように指導しましょう。
まずは質問できるようにすること、次に、すぐに答えを得ようとするのではなく自分なりの考えを持ってから質問するようにすること、このように質問の仕方を指導することで、部下が「自立自走」への道を進めるように支援しましょう。
ステップ3.全体像を考える癖をつけさせる
指示されたことは実行できる、わからないことは自分なりに考えてから質問するようになる、これで「自立自走」できたというわけではありません。よくあるのは、一つ一つの指示に対してどうすればいいのかを考えても、業務全体を考えられていない、つまり指示を「点」として把握はできても「面」として捉えることができていないことがあげられます。普段から管理職が業務について全体像を常に伝えるようにしていたとしても、部下が全体像と各指示を頭の中で繋げて考えられるようになるには至っていないということです。
具体的に説明しましょう。例えば、会議中に出てきた話の中で「これをやっておいて」と上司から指示があったとします。会議が続く中で、他にもいくつか指示されることもあるでしょう。指示された部下は一つ一つの指示に対して、対応を考えます。この時、いくつもの指示の中で同じ案件に関わることがあったり、案件は異なっても一緒に考えたほうがよかったりする場合もあるかもしれません。しかし、往々にして部下は一つ一つの指示への対応に注意がいってしまい、繋げて考えることで効果的に業務を行える、または上司や関係者の理解や確認が得やすい方法があるかもしれないということまで、考えが至らないこともあります。これは、Z世代の部下に限らず、中堅社員であっても起こりうることです。
最終目的、なぜそれをするのかを常に考える癖がついていれば、バラバラにされた指示であっても、一緒に、または繋げて考えたほうがいいかを意識するようになります。最終目的を考えると、どうすれば上司や関係者が理解しやすいか、確認が取りやすいかについても気にすることができるでしょう。
部下の知識や経験が増え、お客様からの問い合わせ対応も含め多様な業務ができるようになると、管理職は新入社員のようなわかりやすい指示をしなくても、依頼したい内容が通じると思ってしまいがちです。その際、部下が一つ一つの指示を「点」として別々にとらえ、最終目的や業務全体像において各指示がどのような位置づけとなっているかを考えて業務を行っているかどうかまで、管理職は把握できていないかもしれません。しかし、全体像を捉える、自分の業務の先にいる人が理解しやすい方法を考えられるようになることは、部下にとっても業務を進めやすくなるといえるでしょう。管理職は、部下からの質問、報告、提案の中で、「点」で見ているなと感じた場合は、全体像を伝え、業務を進めるうえで効果的な方法について考えてみるように指示していきましょう。
バラバラな指示やお客様からの多様なお問い合わせに対して、常に最終目的、または全体像を考える癖を持って部下が業務にあたるようになると、いろいろな状況においても自分なりの意見を持ち、判断、行動できる「自立自走」に近づくことになるでしょう。
部下の「自立自走」を促し、「お膳立て」から脱却しよう
部下が業務、会社に慣れるまでは「お膳立て」がどうしても必要です。しかし、部下の人数が増えていく中で、管理職はいつまでも自分一人でお膳立て対応をしているわけにはいきません。そのため、「自立自走」ができる部下を育成することが大切です。そして「自立自走」ができるようになった部下(先輩社員)には、後輩の指導を任せていくことで、先輩社員を成長に導き、管理職は業務負担の軽減につなげていきましょう。それにより「お膳立て」に費やす時間を、管理職の重要課題であるチームの目標達成に使えるようになるでしょう。
グローネス・コンサルティングではZ世代の部下育成に特化したWithZ研修を提供しています。先輩社員になったZ世代社員向け研修には「自立自走」につながる「発信力研修」や「問題解決研修」があります。カスタマイズの経験も豊富ですので、部下の「自立自走」に向けた取り組みをしたいとお考えの際は、お気軽にご相談ください。