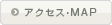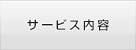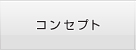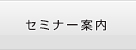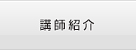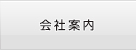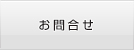部下の「成長」を願わない管理職はいないでしょう。しかし、「成長」は誰かが無理やりさせることが出来るものではなく、知識や経験を得ていく中で本人も知らぬ間に変わっていく、それが「成長」です。そのため、管理職ができることは部下が成長するための支援しかありません。それを「部下育成」という名のもとに管理職は日々頑張っているわけですが、ここでは、「部下育成」の中でも成長支援としての役割が高い、フィードバックについて取り上げます。フィードバックの3つの機会、そして日常のフィードバックで大切な5つのポイントについて説明します。
フィードバックの3つの機会
部下の行動や成果に対して評価や改善点を伝えるフィードバックには主に3つの機会があります。1つめは、今期の評価や来期の目標設定を行う評価面談。年に1回、または上期、下期と年2回行う企業が多いのではないでしょうか。2つめが1on1ミーティング。すべての企業が行っているわけではありませんが、行っている企業では月1ベースが多いかもしれません。そして、3つめが日常のフィードバックになります。フィードバックは機会によって、それぞれ目的が異なります。目的が異なれば管理職が求められる対応法も異なってきます。どのように異なるのか、フィードバックの3つの機会について説明します。
評価面談
評価面談は年に1~2回、目標達成度など今期の活動評価、今後の目標について話し合う大切な部下へのフィードバックの機会です。評価面談の目的は、その名の通り今期の評価を行うことであり、また来期以降の今後の課題設定まで含まれます。具体的な内容としては、部下から自己評価の申告、上司からの評価とその理由、上司からみた課題の設定と今後のアドバイスが主なものと言えるでしょう。管理職の対応としては、部下の自己評価とその理由を把握したうえで、部下が納得できる評価の説明をすることになります。
1on1ミーティング
月に1回など定期的に行われる1on1ミーティング。このミーティングの目的は、部下とのコミュニケーションの機会を定期的に持つことにあります。業務に影響がありそうな部下の悩み等を把握することで、部下が業務をしやすい環境を整えることに役立たせることができます。お互いの理解を深める関係構築につながる機会としても活用できるでしょう。業務に影響を与える内容には業務での悩みだけでなく、健康・メンタル面での悩み、プライベートの悩みも含まれます。管理職の対応としては、部下の悩みに対しフィードバックやアドバイスをすることはもちろん大切ですが、部下の状況を把握することを優先とするため「傾聴」の姿勢が求められます。
日常のフィードバック
社として定められている評価面談や1on1ミーティングと異なり、管理職の判断で行うのが日常のフィードバックです。日常のフィードバックの目的は、部下の日々の言動における課題改善と、部下の良い点を褒める、感謝することにあります。管理職が部下の言動でフィードバックをしたいと思ったときにフィードバックをするので、前もって面談時間が決まっていないこと、また部下からの依頼で管理職がフィードバックに応じるという流れもあることが評価面談や1on1と最も大きな違いとなります。管理職の対応としては、管理職が気になった言動に対し、部下本人はどう感じているのかという部下の認識を先に把握するよう心掛けることが大切といえるでしょう。
日常のフィードバックで大切な5つのポイント
評価面談も1on1ミーティングも部下の成長を支援するには大切なフィードバックの機会です。しかし、普段業務を進めていく中で気になったことを、すべて次のフィードバックの機会まで貯めておくことは難しく、それぞれの面談の目的とそぐわない内容のこともあるでしょう。また時間が経つことでフィードバックの内容が部下に伝わりにくくなることもあります。そのため、気になった時に伝える「日常」のフィードバックは大切であるといえるのです。
では、日常のフィードバックにおいて、どのようなことに気をつけると部下の成長の支援につながるのでしょうか。日常のフィードバックで大切な5つのポイントを紹介します。
ポイント1 事前準備(目的の明確化など)
評価面談や1on1ミーティングでは、どのように伝えるのか、どのような話題から始めるのかなど事前準備をしている管理職は多いでしょう。しかし、日常のフィードバックではどうでしょうか。気がついたときに話をするのに準備が必要?と思った人もいるかもしれません。
なぜ日常のフィードバックでも事前準備が必要なのでしょうか。例えば、チーム内での打ち合わせで素晴らしい提案をした時には「その案、いいね」とすぐに伝えることはいいことです。これには事前準備は必要ないかもしれません。しかし、業務の中で気になることがあったことをいきなり話し出したらどうでしょう。部下はあっけにとられてしまうかもしれません。すぐに伝えるということは、その時の管理職の感情のままに話してしまうリスクもあります。感情のまま話すことの何がいけないかと思うかもしれません。感情のまま=自分に矢印が向いている、つまり部下がどのように受け取るのかなど、部下の状況を考えることが十分にできない状態で話してしまう可能性があるのです。そのような話し方、内容では部下の成長への支援につながるどころか、部下に管理職の意図が伝わらず悩ませてしまうことになるかもしれません。
そのため、日常のフィードバックにおいても事前準備が必要なのです。事前準備でまず大切なのが、「フィードバックの目的の明確化」です。何のためにフィードバックするのかを自分の中で確認しておきましょう。例えば、部下の行動を改善させたい、良い行動だったのでもっと伸ばしてもらいたい、成果を称賛したいなどです。決めておくとフィードバック中に内容がブレることがなくなります。
目的と一緒に押さえておきたいのが、受け取る部下側についてです。フィードバックを受けて、部下にどんな気持ちになってほしいのか、前向きな気持ちなのか、反省してほしいのかということです。また気持ちに加え、その後、どんな行動をとってほしいのかも考えておくといいでしょう。褒めることで、継続してそのような活動をしてほしい。反省を求める場合は、今後の具体的な改善策や期待する行動は何かを考えてほしいなどです。これらを押さえておくと、フィードバック中の部下の発言が、自分の期待と異なることがあれば、伝え方を変えるなどの調整をその場ですることができるでしょう。
ポイント2.具体例となる事実の収集、整理
褒めること、改善を促すこと、どちらのフードバックであっても具体例が必要です。「いつもチームを明るくしてくれてありがとう」と言われても、部下は自分のどんな行動がチームを明るくしているのかがわからなければ、今後どう行動すればいいのかをイメージするのが難しいといえるでしょう。このように、あいまいな言い方では、管理職としては褒めたつもりでも、部下を悩ませてしまうことにつながり兼ねないのです。もちろん反省を促すときも「お客様への対応が悪い」だけでは、何が悪いのか、どう改善すればいいのか、理解するのが難しいといえるのです。
例えば「井上さんは、チームの会議の時、他の人の意見をまずは受け入れてから自分の意見を言ってくれるよね。それによってチームの流れがいつもいい方向に流れるから本当に助かっているよ。先日の会議でも、佐々木さんがC社の営業が強すぎるから営業成績が落ちたって言ったとき、井上さんは、確かにC社の営業はすごいですよね。私の担当しているお客様にもC社の営業が入っていて苦戦しています。でも製品内容がC社と異なる点もあるので、私はそこをお客様に説明するようにしていますよ。って言ってくれて。それがきっかけでC社との製品内容との違いで、どうお客様にアピールするかについてチームで話し合うという方向に持っていくことができた。井上さんが最初にC社の営業は強いことに同意をしてくれたことで、佐々木さんも前向きに製品内容の違いでC社の営業と戦おうと思ってくれたと思う。ありがとう。これからも、チームの活性化に力を貸してほしい」としたらどうでしょう。具体例が入ることで、部下も何を褒められているのか、今後どうしていけばいいのかをイメージしやすいのではないでしょうか。
事前準備で目的や部下にどうなってほしいかを決めたら、次に、その説明に必要な具体例を整理するようにしましょう。具体例があって伝えたいことが出来た場合も、具体例を整理することで、どうすれば部下にうまく伝わるのかを考えていくのがいいでしょう。事前に伝え方のシミュレーションをしておくのも、伝えやすさなどを確認することができるので、お勧めです。
ポイント3.フィードバックのタイミング
事前準備や具体例の整理が出来れば、いつでも部下にフィードバックしていいのかというと、そんなに簡単なことではありません。フィードバックのタイミングは2つの点でとても重要です。1つは、具体例として用意した事実からあまり時間が経たないうちに行うこと。記憶は薄れていくものです。お互いの記憶が十分にあるうちにフィードバックを行いましょう。もう1つが、部下がフィードバックを受け入れる用意が出来ているかということです。例えば緊急性の高い業務に追われている時に、ちょっと時間いいかなと管理職に呼ばれても頭の中は今の業務でいっぱいで、管理職の話が十分に伝わらない可能性が高いといえます。また改善を促すフィードバックを部下が落ち込んでいる時にしても効果は薄いかもしれません。部下の状況を把握して、フィードバックをするタイミングを計るようにしましょう。
ポイント4.部下の認識、部下からの提案を重視
評価面談でも自己評価とその理由から始めることが多いでしょう。日常のフィードバックでも同じです。その時々の具体例で話をする日常のフィードバックのほうが、もしかしたら部下の話を先に聞くことが大切と言えるかもしれません。例えば、お客様への訪問中、部下がお客様の反応に関わらず話を続けていたとしましょう。管理職はお客様が何か質問しかけたことに気がついたとしても、部下はそのことに気がついていなかったかもしれません。そこを確認せず、なんであの時そのまま話をつづけたんだといわれても部下は何のことを言われているのか理解できないでしょう。お客様との打ち合わせについてどう感じた?気になったことはあった?という部下がどのように認識しているかを把握することから始めましょう。部下がどのような認識を持っているかがわかったうえで、自分が気になったことを伝えると、部下はなぜ気がつかなかったのかと考えることが出来るようになります。褒めるときも、部下にとっては当たり前で良い点だと気がついていないかもしれません。それを把握してから褒めるほうが、褒め方に工夫もでき、部下に自信がつくように導くこともできるでしょう。
改善のためのアドバイスも同じです。最初から管理職がアドバスするよりは、どうしていくのがいいと思うと、まず部下に考えさせることが大切です。これにより、すぐに答えを求めず、まずは自分で考えてみるという癖をつけることができます。このようなことの繰り返しが部下の主体性につながり、成長を支援することができるといえるのです。
ポイント5.フィードバックは短時間で簡潔に
評価面談や1on1ミーティングのように、面談時間をあらかじめ確保しているものとは異なり、業務の合間をぬって行う日常のフィードバックは、業務に影響が出ないように短時間で行う必要があります。そのためにも事前準備をしっかりと行い、要点を絞り、簡潔に伝えるように心掛けましょう。そして、先述のように具体例があってから時間をあまり空けずにフードバックを行うことが効果的であるため、頻繁になりすぎないことに注意して適切なタイミングでフィードバックを行うようにすることも大切です。
適切なタイミングでフィードバックを行えるようにするには、短時間で終わるというイメージを部下が持てるようになること、また褒めるためのフィードバックの機会を多く設けることで、フィードバック=改善点を伝えられるというネガティブに思いがちな部下が構えずにフィードバックを受ける気持ちになる(フィードバックを受ける準備がしやすい)状況を作っていくことも必要となるでしょう。
日常のフィードバックを活用して、部下の成長を支援しよう
日常のフィードバックが定着し、部下もフィードバックを受けることに抵抗がなくなる、あるいはフィードバックにより自分のことを知るきっかけになると前向きに捉えられるようになると、フィードバックの効果は高まるでしょう。自分が気づかなかったことを知る、主体的に改善していくことは、部下の成長につながります。日常のフィードバックを活用して、部下の成長を支援しましょう。
グローネス・コンサルティングでは25年以上の研修の実績があります。管理職向け研修、リーダー研修、新人研修など多くの研修プログラムを提供しています。各社に合わせたカスタマイズ研修の経験も豊富ですので、フィードバックの質を高めたいというご要望にも合わせたプログラムをご用意できます。部下育成や管理職としての役割などにお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。