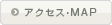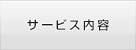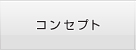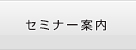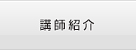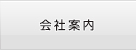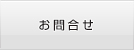主任、係長、課長、部長、経営層と昇進していくにつれ、求められるのが「現場」視点重視から「経営」視点重視という「意識の変化」です。特に課長から部長への昇進はこの変化が求められるといえるでしょう。部長以上になると、会社の成長を考え、経営視点から方針や戦略を立てていかなくてはならない立場になるため、意識の変化を求められるのは当然のことだといえるかもしれません。一方、経営視点で物事を考えるのだから、現場が理解できなくなっても支障はないといえるのでしょうか。「現場視点重視から経営視点重視になること」=「現場視点が必要なくなる」にはならないでしょう。ここでは、部長になっても現場の理解が大切な理由と、その対応法について考えていきます。
部長になって変化すること
「現場視点」重視から「経営視点」重視へと、部長に求められる意識の変化に大きな影響を与えるのが、行動の変化といえるでしょう。具体的に何が変わるのでしょうか。ここでは意識の変化に大きく影響し、現場理解を難しくする要因となる2つの行動変化について説明します。
行動の変化1:戦略・戦術の実行から戦略策定へ
部長になれば、会社全体、組織全体を考えた「戦略の策定」が重要な業務になってきます。戦略の策定には、PEST分析と呼ばれるような、政治的、経済的、社会的、技術的な環境の変化をみていく必要があり、また競合、顧客の動きなど市場動向にも注意を払わなければならないでしょう。もちろん社内のリソースや強みの把握なくしては戦略の策定はできませんが、社外の情報、環境の変化への注視は重要であるといえます。
一方、課長など現場に近い管理職は、上層部で決められた戦略の基、具体的な戦術、施策に落とし込み、実行することが重要な業務となります。施策を実行するには、部下の役割分担や進捗管理、部下のサポートなど現場の状況を把握することなしでは、結果につなげるは難しいといえます。
つまり部長になると、業務が戦略・戦術の実行から戦略策定へ移行するため、現場から離れた行動が中心となるのです。
行動の変化2;現場部下との関わりが直接的から間接的へ
部長になり、上層部や他部署との連携、必要に応じて外部との連携が求められるようになると、普段接する人たちが変わってきます。現場で頑張る部下に指示をし、業務のサポートをするのは直接の上司である課長や係長の役割となります。部長になれば、現場の部下に直接指示を出すことはほとんどなくなります。「直接指示を出さない」=「普段業務でのつながりはなくなる」、つまり直接かかわる機会が大きく減り、課長などが間に入った「間接的な」関わりが中心となるでしょう。
現場理解が必要な理由
現場で施策を実施する機会が減り、現場にいる部下との関わりも間接的になれば、現場の理解が希薄になるのは自然なことかもしれません。しかし、だからといって現場の理解を忘れても成り立つというほど、部長の業務や責任は甘いものではありません。現場を理解していないために起こり得る2つのリスクについて説明します。
リスク1:机上の空論になる可能性
先述したように、会社の方針、戦略を立てるには、社外の情報、環境の変化への注視が必要となります。これには競合の動きや顧客の動向ももちろん入ります。これらを基に自社が目指すもの、リソース、強みなどを加味して戦略を立てていきます。戦略は目標達成にむけた中長期的な計画のため、課長が現場の状況を鑑みて戦術や施策に落とし込めば、部長は現場の理解が浅くても問題ないともいえるかもしれません。しかし、現場だから見えることもあります。戦略を立てるときに入手した資料やデータでは見えない部分に気がつかず戦略を立てると、いくら中長期的な計画であるとはいえ、現場ではどう対応していいのかわからないものになっている可能性もあるのです。経営視点、広い視野は会社の成長のためには重要なことですが、足元の確認を怠ると、踏み出したら泥濘で進めないというリスクの可能性があることも気にしておく必要があるでしょう。
リスク2:方針変更や戦略立て直し対応の遅れ
中長期的な方針や戦略であっても、社内の状況や競合、社会などの環境の変化によって立て直しが必要となることもあるでしょう。社内外に限らず、環境の変化は、誰もが知る変化となる前に、小さな予兆がいろいろなところで起こっているものです。この小さな予兆は、部長が外部との交流などで気がつくこともあれば、現場だからこそ気がつくこともあるでしょう。現場では小さな予兆に気がついていても、最終的にどんな変化になるのかの予想がつかなければ、現場内で話題に上がることがあっても部長まで報告するには早いと考えてしまうかもしれません。もしかしたら、ちょっと気になる程度で大きな変化につながる予兆だと捉えていない場合もあるでしょう。このような現場で起きている予兆を知ることは現場を離れている部長には難しく、誰もが知る変化となってから戦略の立て直しをすることを迫られ、対応が遅れる可能性があるのです。
現場理解を忘れないために
現場から離れてしまうと現場の理解が難しくなることは当然のことですが、現場を軽視してしまうと、せっかく立てた戦略なのに、現場でそれに沿った施策がうまく立てられず業績が伸びない、戦略の立て直しが必要なことに気がつかず機を逃すリスクがあることがわかりました。ここでは現場理解を忘れないために、部長になってもできることについて考えてみましょう。
現場の理解ができるルートの確保
現場理解が必要だからといって、部長が現場の部下に直接指示を出す、たびたびお客様訪問に同行するなどをしていては、部長としての業務が出来なくなってしまいます。それでは本末転倒です。自分が直接動かなくても現場を理解するためのルートを作っておくことが必要となります。つまり、現場をよく知る係長や課長を通じて情報を得るのです。課長が部長への報告を行うのは当然のことなので、ルートの確保は不要と思われるかもしれません。課長から部長への報告内容が業績など結果だけではなく、課長の目を通して現場で起こっていること、気になっていることも合わせて伝えてもらうようにすること、それが現場の理解のための「ルート」となります。それには、部長が何を気にしているのか、現場の何を知りたいのかということを課長に理解しもらい、報告の際に部長が気にしている現場の状況についても伝えてもえるようにする「ルートの確保」が重要なのです。
現場社員との交流機会
人はそれぞれ気にする点が異なります。現場の理解ができるルートを確保したとしても、課長の目を通した現場のため、課長が気にならなずに報告しなかったことでも部長が現場にいたら気になったこともあるかもしれません。それを解消するのが、現場の部下たちとの交流の機会を持つことです。頻繁にする時間的余裕はないかもしれませんが、数か月に1度、半期に1度でも直接交流を持つ機会を持つことは大事なことといえるでしょう。現場、部下を理解できるだけでなく、現場の感覚から学びや新たな発見があるかもしれません。頻度は少なくても直接現場と接する機会を大切にしましょう。
現場とともに会社を成長に導こう
昇進していけば、責任も大きくなります。会社を成長に導くために、奮闘することも多いでしょう。しかし、現場があってはじめて会社は成り立ちます。経営視点重視の立場になっても、現場を理解し、現場を大切にしていきましょう。そして、現場とともに会社を成長させていきましょう。
グローネス・コンサルティングでは25年以上の研修の実績があります。管理職向け研修、リーダー研修、新人研修など多くの研修プログラムを提供しています。各社に合わせたカスタマイズ研修の経験も豊富ですので、悩める管理職を元気にしたい!というご要望にも合わせたプログラムをご用意できます。部下育成や管理職としての役割などにお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。